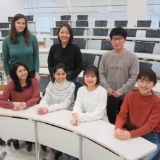ダイヤモンド社カリスマ編集者加藤貞顕氏(准教授 富山栄子)
授業のゲストスピーカーとしてダイヤモンド社カリスマ編集者、加藤貞顕氏に「出版のマーケティング」についてお話していただきました。加藤さんは1973年新潟市生まれ。大学院で経済学の修士号を取得後、アスキーに入社され、『英語耳』というヒット作を出しました。
その後、2004年よりダイヤモンド社に移籍し、『投資信託にだまされるな!』、『スタバではグランデを買え!』、『マイ・ドリーム』などのベストセラーを手がけてこられました。
さて、どうやればベストセラーは生まれるのでしょうか?
ポイントは作り手の興味あるテーマと「みんな」の興味があるテーマをクロスさせることにあるそうです。
5000部刷ると増刷率は3割程度。増刷したらシングルヒットで、1万部超でツーベースヒット。だめな例は、ただ自分を語るだけの本、書けるから書いた本、有名人だから出した本で、これらは作り手の都合だけで作られた本だからだそうです。
1億人が日本の人口だとすると本を買う可能性がある数は1%(本の部数=潜在顧客の1%が最大(1%の法則)。
では、1億人が興味あるテーマとは、例えば家族、愛、友情、人生などのテーマ。
要するに、誰でも身近に感じられるテーマですね。女性だったら、「美しくなるには(?)」男性だったら「モテるには(?)」あたりでしょうか?
本はテーマのほかにも、内容と書き手で差別化が必須です。
たとえば、大ヒットした『投資信託にだまされるな』では、対象顧客は高齢者と若者(将来に不安をかかえている)。文字は大きく、易しい口調、かわいいデザインで。悪い書き方は、読者を上から啓蒙する。ひどい投資信託や業界をたたく。もしくはほめたたえる。こうした作り手側の都合で作ると売れないそうです。社会に知識が届かないばかりか、全員が損をします。
そこで加藤氏は考えました・・「書く側と読者の交差点はどこなのか?」
そして、ひどい投資信託の解説を楽しく行う。知識&エンターテイメントでポジティブな代替案を出すことで、希望のある結論を出すことで、成功しました。
別のヒット作『スタバではグランデを買え!』(24万部の大ヒット)は、経済学で社会の仕組みを解説する本で多岐にわたる内容です。教養っぽいテーマでは明確な「得」が提示しにくい。こうした本は「タイトルが重要」で面白そうと思ってもらうしかないそうです。まともに『経済学でわかる価格の仕組み』などというタイトルではダメ。そこで一番おもしろいものをひとつだけ取り出したそうです。
同書は内容もいいですが、いかに編集者の「タイトル」付けという力量が売れ行きに影響を与えるのかがよくわかります。
私も同書を読みましたが、一番おもしろいと思ったのは「お茶」の価格が違うのになぜ消費者は高い150円でペットボトルの「お茶」を買うのかという点でした。同書を読んでから、著者の吉本先生が出演しておられたNHKの番組も見ましたが、「機会費用」などのわかりにくい経済学の概念を、わかるように説明していると感心しました。
一方、我々一般人が本を出版するにはどうしたらいいのでしょう?とくに起業家にとっては、本の出版は信頼度アップ(名刺代わり)になります。本を出すには、本業で名をなす、出版社に売り込みをする。お金を払う場合の3通りがあります。
最もお薦めなのは、自分で良い企画書を作って、興味の一致する版元の、興味の一致する編集者へ電話してから送ると成功率が高いそうです。一週間して返事がないならダメで他の出版社をあたるとよいそうです。ディスカバー21、大和書房、三島社など、小さく、新しい出版社はやる気があるそうです。または、出版エージェントを使うのも成功率が高いそうです。エリエス・ブック・コンサルティングやアップルシード・エージェンシーなどです。これらはお金はかかりますが、企画にあった編集者を紹介してもらえるのだそうです。
番外編としてはブログだそうで、これだとコンテンツがたまり、書き方が鍛えられ、内容と筆力を審査してもらえるのだそうです。うまくいっている例が梅田望夫、小飼弾
だそうです。しかし、更新が大変でもめごとがおこることもあるので、筆力と覚悟が必要とのことでした。
さて、このヒットメーカー加藤氏の最新作が、落希一郎著『僕がワイナリーをつくった理由』>(ダイヤモンド社)です。加藤氏は、落氏のワイン作りへの思い、こだわりに魅了され、同書の企画を著者へもちこんだそうです。「本物の」ワイン作りに人生をかけた男の奮闘記です。同書の最後のくだり「人間思い続ければできるものです。あなただって、僕だってかなりのことができます。そう、自分の人生をかければ。」(185頁)には、目頭が熱くなり、感動しました。同書の書評はまた次の機会に書くことにします。